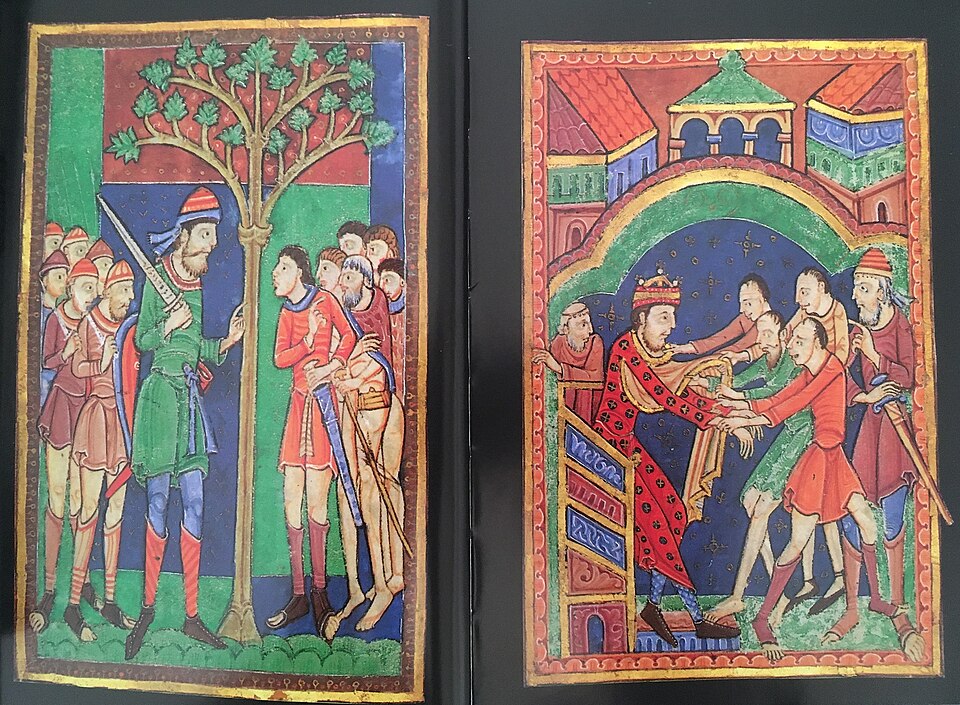ヴァイキングとバイキングの違いって?
中世においてヨーロッパ中を震撼させた北欧出身の海洋民族は、「ヴァイキング」と呼ばれますが、記述としては「バイキング」と書かれることも多いですよね。果たしてどっちが正しいの?という疑問は当然出てくることかと思います。そこでこの記事では、ヴァイキングとバイキングの語源や意味、そして日本で「食べ放題形式」を指す用語として定着している「バイキング料理」との関係なんかも解説していきます。
|
|
|
|
|
|
ヴァイキング(viking)の語源
ヴァイキングとは、8世紀から11世紀にかけて活躍した北欧の戦士や冒険者を指します。語源は古ノルド語の「víkingr」で、これは「遠征者」や「海賊」を意味していました。この時代、ヴァイキングたちは戦闘や交易、探検などでヨーロッパ各地を跋扈していました。彼らの活動は広範囲にわたり、影響は現代の文化にも残っています。
|
|
|
「バイキング」記述でも意味は同じ
「バイキング」とカタカナ表記されることもありますが、その意味はヴァイキングと同じです。これは日本語特有の表現であり、音の違いによって表記が変わるのみです。英語圏では一貫して「viking」と綴られ、発音も「ヴァイキング」に近いものです。
「ヴァイキング」記述が一般的
日本では「ヴァイキング」と「バイキング」の両方が使われますが、近年は「ヴァイキング」という表記が主流です。これは音が原語に近いことと、言葉の正確さを求める風潮が背景にあります。例えば、歴史書や学術的な文章では「ヴァイキング」と表記されることがほとんどですね。
|
|
|
食べ放題の「バイキング料理」との関係
さて、ここで気になるのが、日本でよく知られている「バイキング料理」との関係です。この用語は、1958年に日本のホテルで初めて取り入れられたビュッフェ形式を指し、映画『バイキング』(1958年)の影響を受けて名づけられたという背景があります。この映画では勇敢なヴァイキングたちの豪快な宴会シーンが登場し、これが「たくさん食べられる」というイメージと結びついて、「バイキング」と呼ばれるようになったようです。
以上、ヴァイキングとバイキングの違いについての解説でした!
ざっくりと振り返れば
- 「ヴァイキング」は北欧の戦士や冒険者を指す言葉で、語源は古ノルド語に由来
- 「バイキング」も同じ意味だが、日本では音の違いとして扱われる
- 「バイキング料理」は映画の影響で生まれた、日本独自の食べ放題形式の呼び名
・・・という具合にまとめられるでしょう。
ようは「ヴァイキングとバイキングは意味が同じでも、使い方や発展には文化的な違いがある」という点を抑えておきましょう!
|
|
|